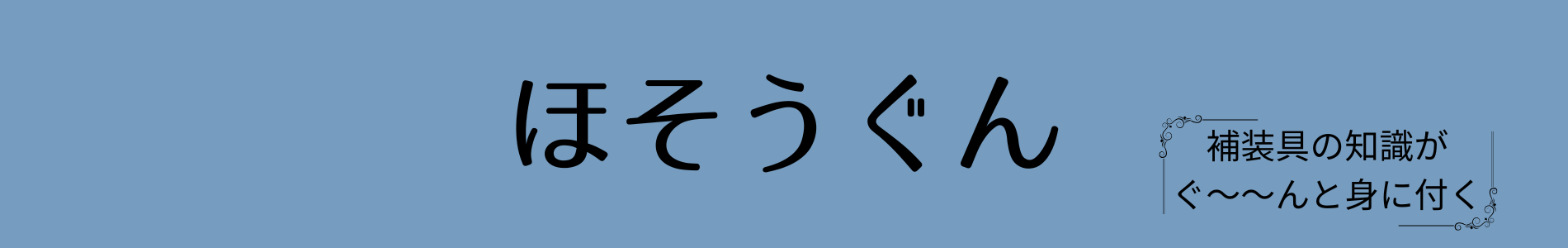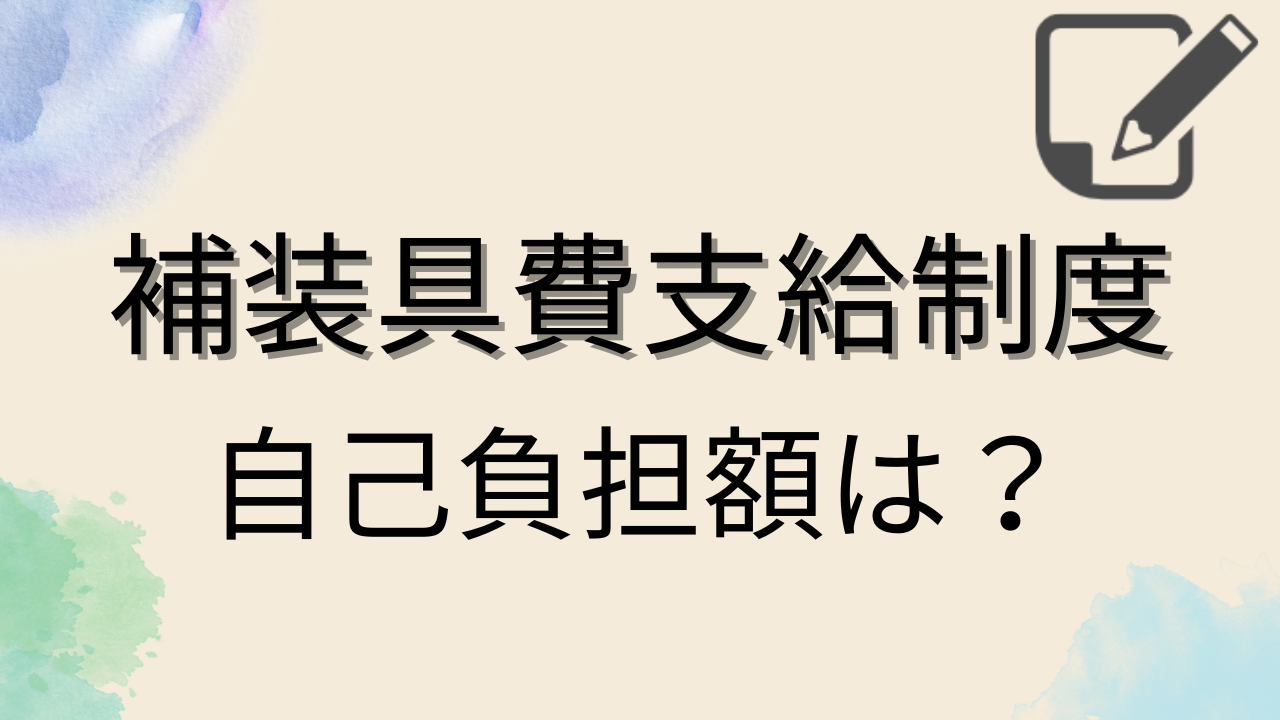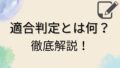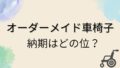・制度を使った場合の負担額は?
・負担額はどのように決まる?
補装具の会社で事務員として10年以上働いている私が、上記などのお悩みを解決出来る記事を書きました!
補装具費支給制度を利用しようと思っているけど、詳細が難しそう……。
そう感じている方も多いのではないではないでしょうか?
この記事では、制度の自己負担額について分かりやすく解説していますよ。
是非最後までご覧下さいね。
補装具費支給制度の自己負担額の基礎知識3つ

補装具費支給制度の自己負担額の、知っておくと役に立つ基礎知識を紹介しますね。
・原則は1割負担
・基準額について
・差額について
上記3つについて見て行きましょう。
原則は1割負担
補装具の購入・修理にかかる費用の、1割を利用者が負担する決まりとなっています。
これを利用者負担金(自己負担額)と言います。
1割と言いましたが、支払わなくていい(つまり0円)ケースも結構あります。
各市町村の判断によるので、0円だったらラッキーといった感じ。
でも何十万もする補装具を製作する場合、1割でもかなり負担がありそう……。
と不安に思う方もいるかと思います。
そんな事態への対策として、上限額が定められています。
詳細については後程詳しく解説しますね。
基準額について
基準額とは、補装具費の申請で決定が下りた金額です。
厚生労働省が定めている項目に従って、補装具業者が見積書を作って市町村に提出します。
この基準額を基に、利用者負担金が決定するのです。
差額について
補装具費支給制度で認められない項目の製作を希望した場合は、全額自己負担(差額と言う)となります。
オーダーメイドで車椅子を製作する場合、例えばフレームカラーやスポークカバーの柄などといった、個人の好みをプラスするための要素は基本的に差額になります。
補装具費支給制度の負担上限月額の基礎知識3つ

自己負担額には上限が決まっています。
抑えておきたいポイントは下記の3つ。
・負担上限額月額
・上限が設定されている理由
・所得区分ごとの負担上限額
負担上限月額
全国どこの地域でも37,200円が上限とされています。
上限が設定されている理由
『補装具を製作して生活のサポートに使いたい。なくては困る』
という方は多くいらっしゃるかと思います。
利用者負担金の上限が決められていなかったら、補装具費支給制度を使っても負担が大きくて補装具を製作出来ない可能性もあります。
そんなことを防ぐために上限37,200円が定められているのです。
所得区分ごとの負担上限額
世帯収入によって負担額の上限は変わってきます。
それは下記の通り。
生活保護世帯・住民税非課税世帯 → 0円
住民税課税世帯負担上限額 → 37,200円
ここで追加知識。
『補装具業者に生活保護世帯などと知られてしまうのではないか』
といった疑問を感じるケースもあるかもしれませんが、業者がそのようなことを知ることはありません。
というのも私は事務員なので、数えきれない位たくさんの市町村と書類のやり取りをしていますが、生活保護世帯や住民税非課税世帯といった情報は書かれていないので安心して下さいね。
補装具費支給制度の自己負担額に関する注意点2つ

制度を利用する際に、知っておくべき注意点を解説しますね。
・高額所得世帯の申請について
・利用者負担金の支払先について
わざわざ書かなくても良いかもしれませんが、頭に入れておくと役立つかもしれません。
高額所得世帯の申請について
高額所得世帯の場合、補装具費支給制度の利用を申請しても認められません。
その場合、全額自費で製作する必要があります。
利用者負担金の支払先について
『市町村に申請して利用する制度だから、利用者負担金は市町村に払うんじゃないの?』
と思うかもしれませんが、それは違います。
利用者負担金は補装具を製作する業者に支払います。
市町村や業者から事前に説明があるとは思いますが……。
追伸:毎日がんばっている『あなたへ』
慣れないたくさんの新しい情報を探すのは大変ですよね。
いつも本当にお疲れ様です。
毎日気が張っていると、心がすり減ってしまいますよね。
そんな時は身体を動かして汗をかいてリフレッシュしてみませんか?
私も実際にヨガをしていますが、事務仕事による肩や首の凝りが圧倒的に軽くなったのを実感しています。
・手ぶら&0円で滝汗を流してリフレッシュできるLAVA
・ひっそり自宅で受けられるSOELU
今のあなたに合った「自分へのご褒美」を選んでみて下さいね。
まとめ
補装具費支給制度の自己負担額について解説しました。
重要ポイントをまとめると下記のようになります。
・上限は37,200円
・世帯収入によって負担額が変わる
・0円の場合もある
以上を覚えておけば、お金の用意にも余裕を持てるかもしれませんよ。
補装具支給制度については、下記の記事で詳しく解説しています。
良ければ参考にしてみて下さいね。