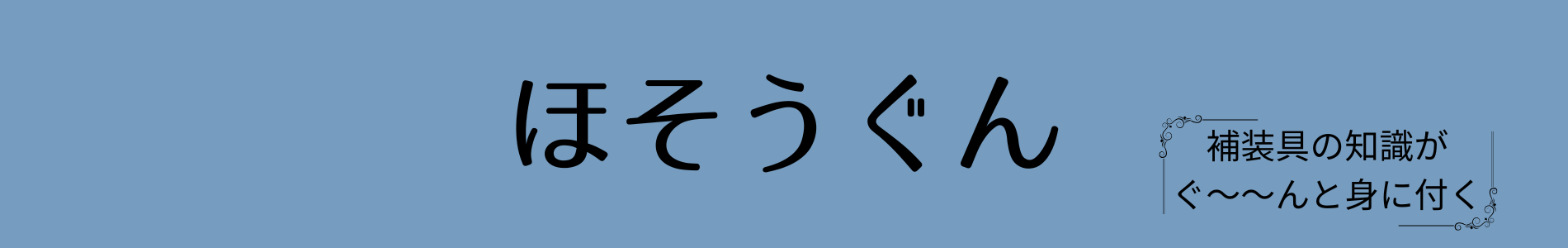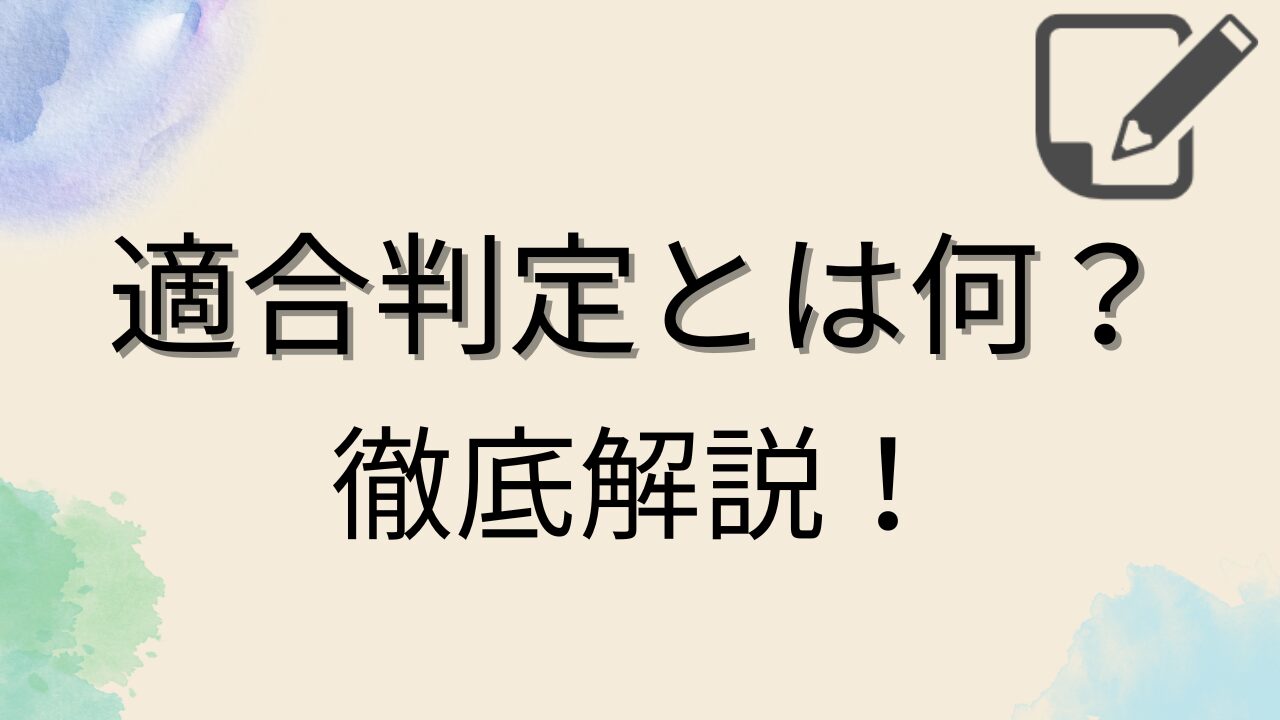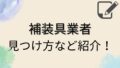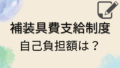・適合判定の内容は?
・どこでやるの?
補装具の会社で事務員として10年以上働いている私が、上記などのお悩みを解決出来る記事を書きました!
補装具を作る際に適合判定というものをやる必要があると言われたけど、詳細が分からない……。
という方は多いかと思います。
この記事を読めば内容や一連の流れ、注意点などが分かって、焦らずスムーズに進めることが出来るはずです。
是非最後までご覧下さいね。
補装具費支給制度ってそもそもなに?

補装具費支給制度とは、障がいのある方が日常生活や社会生活を送るうえで、必要な補装具(義足、車椅子など)を購入・修理するための費用を支援する公的な制度です。
詳しくは下記の記事で紹介しているので、良ければ参考にしてみて下さいね。
適合判定について知っておくべきポイント6つ
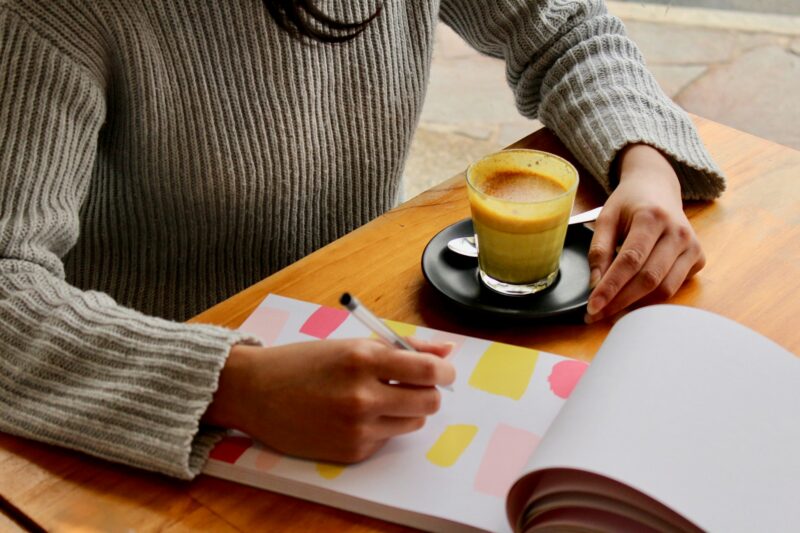
適合判定について、これは知っておいてほしい! というポイントをまとめてみました。
それは下記のような項目になります。
・適合判定とは?
・適合判定の重要性
・適合判定が適用される年齢
・どこから連絡が来る?
・どこでやるの?
・いつでもやっているの?
それぞれ見て行きましょう。
適合判定とは?
適合判定とは簡単に言うと、補装具を使用する人の身体に、どんな補装具が最適なのか。
それを見極めるための場になります。
適合判定の重要性
身体に合った補装具を作るためには、専門知識を持った方の意見が重要です。
支給を申請した補装具が、利用者の身体状況や生活環境に合っているか、そして必要性があるかを専門家と話していく中で、自分の身体に合った補装具を作ることが出来るのです。
適合判定が適用される年齢は?
18歳以上が対象となっています。
どこから連絡が来るの?
お住まいの地域を管轄している、役所から連絡が来ます。
どこでやるの?
お住まいの地域の、県のリハビリテーションセンターなどで行います。
いつでもやっているの?
いつでも判定を受けられる訳ではありません。
多くの方が利用するため、日程が結構パンパンなことが多いので、日時を細かく指定されることがあります。
適合判定の具体的な流れとチェックポイント5つ

適合判定の具体的な流れとチェックポイントを解説しますね。
申請から判定までのステップは下記のような感じです。
・市区町村の窓口で相談・申請
・見積書と意見書作成
・専門機関(判定機関)でで行う日時の調整
・判定への立ち合い
・支給決定
それぞれ詳しく解説します。
市区町村の窓口で相談・申請
補装具費支給制度の申請は、お住まいの地域の役所の障害福祉課に行く必要があります。
そして、補装具の製作で18歳以上の場合、適合判定について案内がされます。
見積書と意見書作成
見積もりは補装具業者が作り、意見書は通所先などの理学療法士や作業療法士の先生が作ります。
専門機関(判定機関)で行う日時の調整
上記の申請と書類の用意が出来たら、いよいよ判定。
制度の利用者と、業者と、判定機関の都合が合致する日時となります。
これがなかなか予定が合わずに、日にちが先に延びてしまったりします……。
判定への立ち合い
身体障害者更生相談所や医療機関の医師、義肢装具士などの専門家が行います。
補装具業者も立ち会いますが、基本的には聞かれたことに答えるのがメインとなります。
支給決定
希望している補装具が本当に必要な物。という風に判定で認められたら、やっと支給決定が下ります。
適合判定でチェックされること4つ
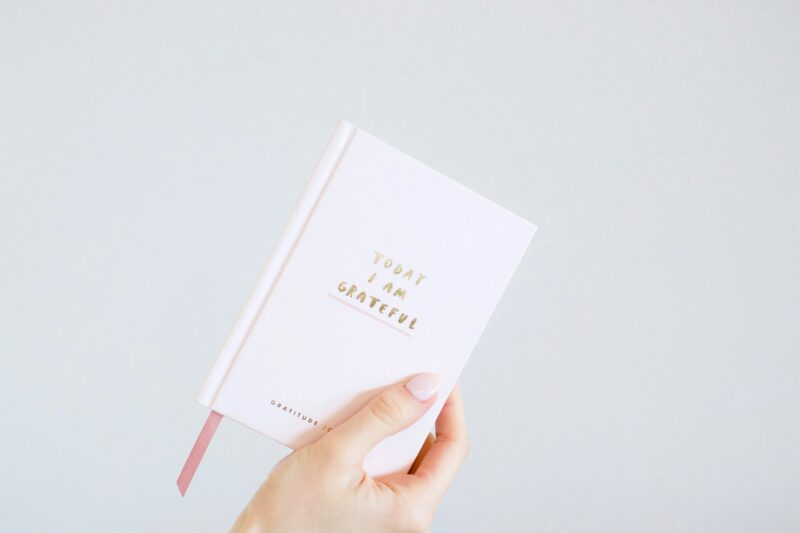
適合判定でチェックされることについて簡単に説明しますね。
それは下記のようなことになります。
・医学的所見
・身体計測
・生活状況
・補装具の必要性
ではそれぞれ見て行きましょう。
医学的所見
現状の身体機能や、どのような補装具が適しているかをチェックされます。
身体計測
補装具のサイズや仕様が身体に合っているかなどチェックされます。
生活状況
どのような場面で補装具が必要になるか(自宅内、外出時など)チェックされます。
自宅内の構造などについても聞かれます。
それはなぜかというと、自宅内でも車椅子を使う場合、車椅子が入らなかったりすると困るので、玄関や室内のドアの幅などを確認されることがります。
補装具の必要性
日常生活や社会生活を送るうえで、その補装具が不可欠かどうかチェックされます。
適合判定について役立つ豆知識3つ

適合判定に臨む前に、心がけておくと良いかもしれないポイントをご紹介しますね。
それは下記の3つです。
・無理に張り切らない
・希望が全て通るとは限らない
・補装具業者だから書ける裏話
それぞれ見て行きましょう!
無理に張り切らない
判定の際に、『これ出来ます!』といった感じで動けることを、無理してアピールする方もいらっしゃいます。
見られている場でそのような気持ちになることは分かりますが、実際これはよくありません。
というのも、日常生活の中での動きを知ってもらうことが重要だからです。
一時的に無理をして動いて、その動きが常にできるという風に判定員の方に勘違いされてしまうと、本来の体の動きには合っていない補装具が出来てしまう可能性があるのです。
なので無理は禁物。
希望が全て通るとは限らない
あれも欲しい! この機能も欲しい!
より良い補装具を使いたいという思いから、色々と機能をプラスしたいという思いは分かるのですが、希望全てが通るとは限りません。
『認められたらラッキー』位に考えていた方が良いかと思います。
補装具業者だから書ける裏話
私の会社では判定への立ち合いはちょくちょく行っているのですが、その中で感じていることがあります。
それは下記のようなこと。
・判定員によって対応が違ってくる
・県によっても対応が違ってくる
業者からしたら『え、その判断おかしくない?』と思うが多々あります。
かと思えは逆に『え、それ認めてくれるの?』といったケースも。
なんというか判定する人や判定場所によって、大きく価値観が違っている印象なので、『なんだかなぁ……』
と感じてしまっています。
まとめ:適合判定は安心・安全な補装具利用の第一歩
適合判定は、単なる手続きではなく、本当に自分に合った補装具を手に入れるための重要なプロセスです。
しっかりと準備をして、安心して補装具を活用しましょう!