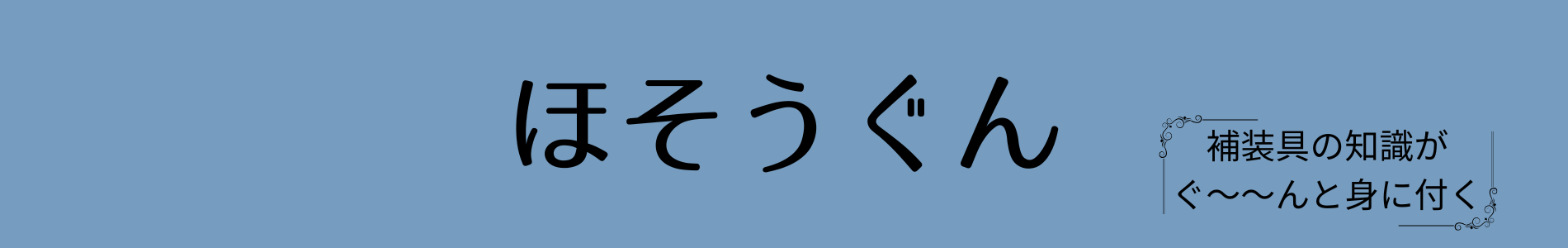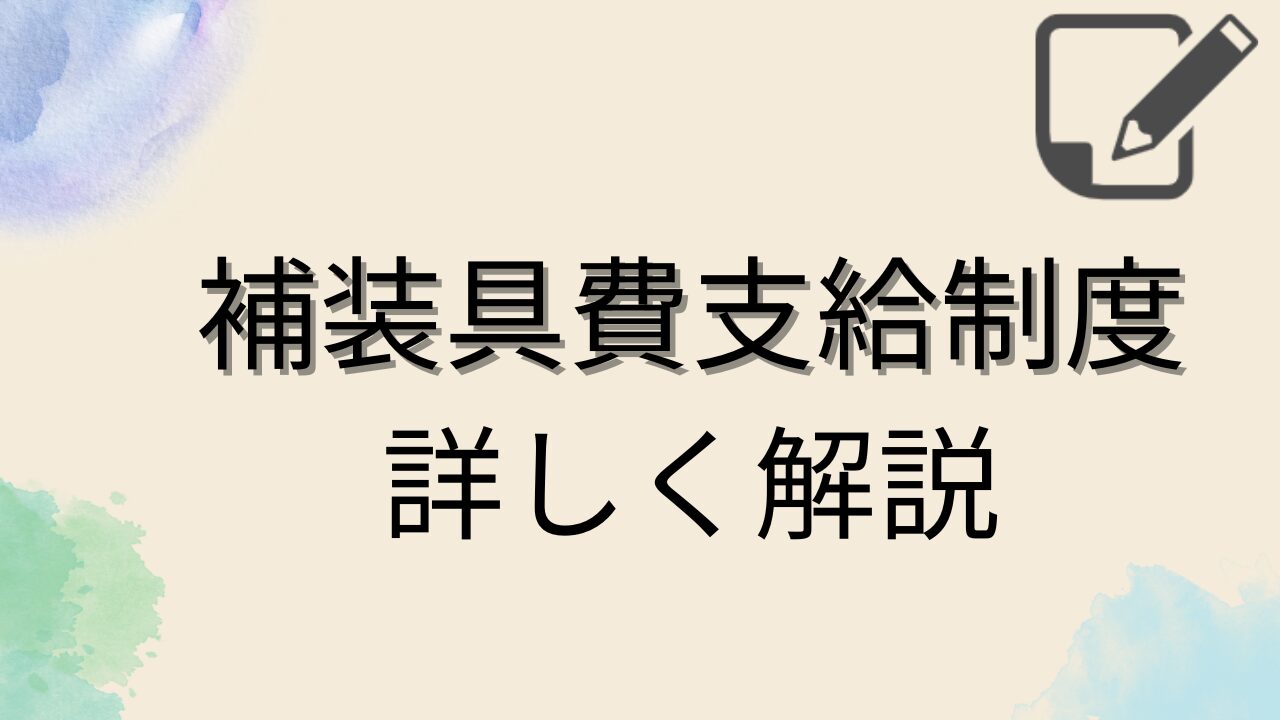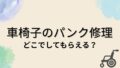・補装具費支給制度の申請方法がよく分からない……
・お金はかかるの?
補装具の会社で事務員として10年以上働いている私が、上記などのお悩みを解決出来る記事を書きました!
補装具費支給制度とネットで検索すると、堅苦しい文章ばかりで正直分かりづらいかもしれません。
そこで!
補装具の会社で10年以上事務員として働いている私が、裏話なども交えて分かりやすく記事にまとめてみました。
これを読めば、制度について深く理解できるようになりますよ。
制度の申請から補装具の納品まで、一通りの流れを解説しているので、最後までご覧下さいね。
※補装具の製作・購入や修理に関しては、医療関係者や業者の意見を聞くことが重要です。
以上の点を頭に入れておいていただければと思います。
補装具費支給制度の詳細

補装具費支給制度は厚生労働省が定めている制度で、毎年改定されています。
一般社団法人の日本義肢協会というのが制度について業者向けに資料を発行しているのですが、それも参考にしながら詳細を紹介して行きますね。
補装具費支給制度の目的
制度の目的について、厚生労働省のホームページでは下記のように解説されています。
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的
引用:補装具費支給制度の概要/厚生労働省
日常生活のサポートをするために、車椅子や装具などを提供するための制度となっています。
ちなみに補装具の製作や修理についての相談&申請は、市町村が窓口となっています。
対象者
障害や難病を持っている方などが対象となっています。
申請には障害者手帳が必要となります。
料金について
例えばオーダーメイドで車椅子(クッション部分もオーダー)の場合50万円位かかることは当たり前です。
その大きな金額を、車椅子を必要としている本人や家族が払うのは大変ですよね。
そこで導入されているのが、代理受領方式という仕組みです。
お住まいの地域の市町村が補装具の購入・修理費用の一部を負担することで、利用者の支払う金額が大幅に抑えられるのです。
更に詳しく解説すると、納品までにかかった費用を業者が一時的に負担し、納品完了後に市町村に請求をしています。
この仕組みのおかげで、利用者が負担する金額は1割(上限37,200円)のみとなります。
※利用者負担の支払いについては世帯収入なども関わってくるので、詳しくは市町村に問い合わせてみて下さいね。
収入が多いと、そもそも制度の利用を認めてくれないケースもあります。
補装具費支給制度の流れについて
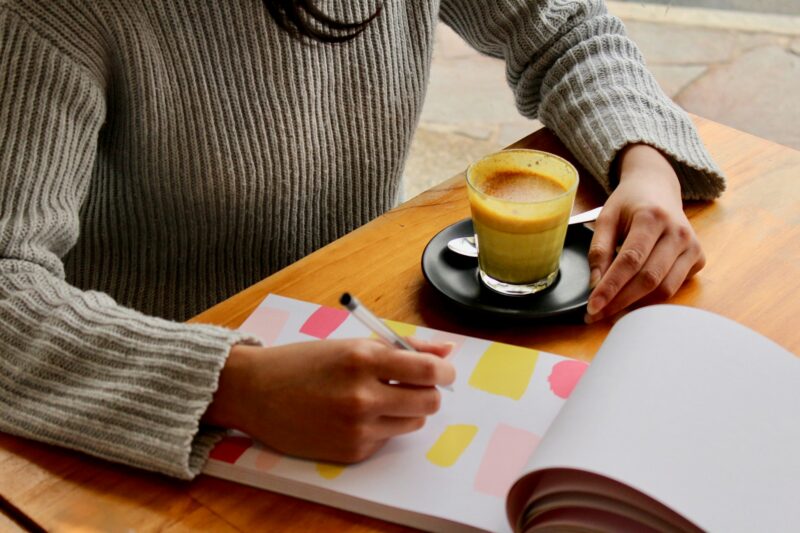
ここらからは、制度の申請から受け取りまでの流れについて解説しますね。
申請先
先程も述べましたが、申請先はお住まいの地域の市町村になります。
地域によって窓口の名称が障害福祉係だったり福祉課だったり身体障害課などなど……。
問い合わせる時に『補装具の申請について』と言えば伝わります。
(毎日のように各市役所から問い合わせを受ける私からしたら、なんで名称バラバラなのかいつも疑問に思っています……)
申請をする時は、窓口に直接申請に行くと手間が省けますよ。
というのも、電話だけで申請を済ますことが出来ないからです。
補装具申請書という書類を書く必要があります。
他にも必要な書類があり、それは下記のようなもの。
・医師の意見書
・見積書
・身体障害者手帳
意見書については、補装具を使用する方が利用している施設で働いている、理学療法士や作業療法士の方に書いてもらう書類。
見積書に関しては補装具業者が発行します。
市町村によって書類も変わってくると思うので、要確認。
審査
必要書類を提出したら、すぐに制度の利用が認められるという訳ではありません。
書類や申請者の意見を参考にし、市町村は更生相談所などの意見も聞きながら、『本当にこの補装具が必要なものなの?』と判断することになります。
ちなみに、補装具の利用者が18歳以上の場合、適合判定というのを行うことがあります。
詳細はというと、お住いの県の総合リハビリテーションセンターなどの施設に利用者と家族、そして業者が行き、センターの職員から色々と質問されたりするのです。
体調や距離の問題でセンターなどに行けない場合、書類を送付する形式で済む書類判定もありますよ。
詳しくは窓口で問い合わせてみてくださいね。
支給決定
審査の結果、支給が決定されると下記のような書類が発行されます。
・通知書
・支給券
・委任状
通知書は利用者の家に送られますが、支給券と委任状については業者に送られることもあります。
申請書類の全てが市町村に届いてから、支給決定が下りるまでは大体1~2週間程かかります。
製作や修理の開始
支給決定の書類が発行されたら、業者が補装具の製作や修理を開始します。
※支給決定前の製作や修理は出来ません。
もしやってしまうと市町村から怒られて、今後補装具を製作できなくなる可能性もあります。
(ルールがあるのは分かるけど、少し融通利かせてくれてもいいんじゃないかなぁ……というケースもあったりしてモヤモヤします)
補装具費支給制度についてよくある質問
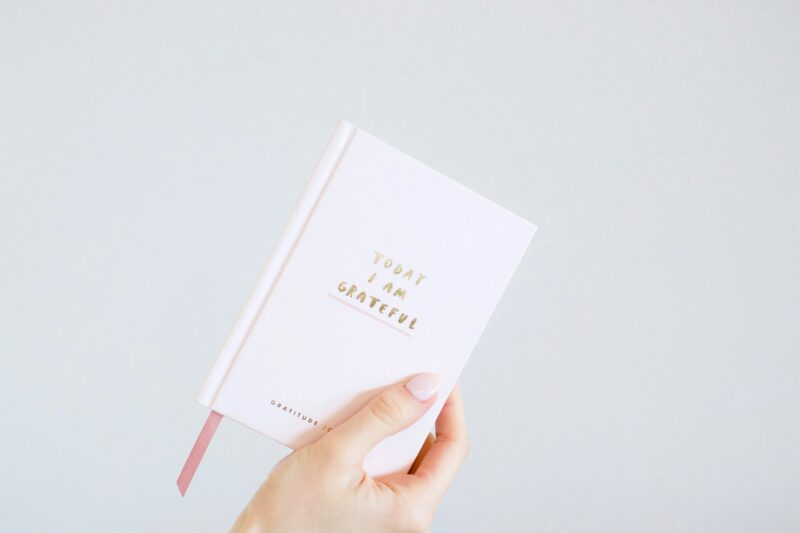
制度の利用者から、問い合わせの多い質問をまとめてみました。
Q:申請すれば必ず認められますか?
A:必ずではありません。
というのも年々支給決定を認めるかどうかの基準が厳しくなってきています。
特にここ数年その傾向が強くなっているように感じています。
例えば海外製の車椅子や電動車椅子などの値段が高い物は、認めてくれないケースが非常に多いです。
Q: 今使っている補装具の修理にも使えますか?
A: 修理にも使えます。ただし製作から少しの期間しか経っていない物だと、認められない可能性もあります。
しかし、タイヤパンクやキャスターの破損などの場合は数か月後でも認められる可能性があります。
理由としては消耗品だし、走行に支障が出るからです。
Q:車椅子や座位保持装置はどの位の期間で作り変えが出来る?
A:車椅子は6年、座位保持装置は3年です。
Q:車椅子は何台作れる?
A:基本的には1台です。ただし例外もあり、車椅子利用者が学校に通っている場合、自宅用と学校用でそれぞれ1台ずつ作れるケースもあります。
まとめ:補装具費支給制度を活用してより豊かな生活を!
補装具費支給制度について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
制度の仕組みやルールについて理解が深まると、いざとなった時に焦らずに行動することが出来ますよ。