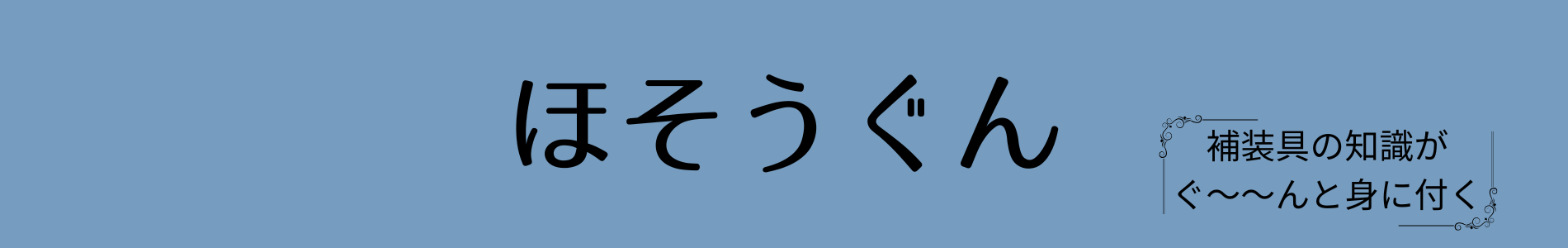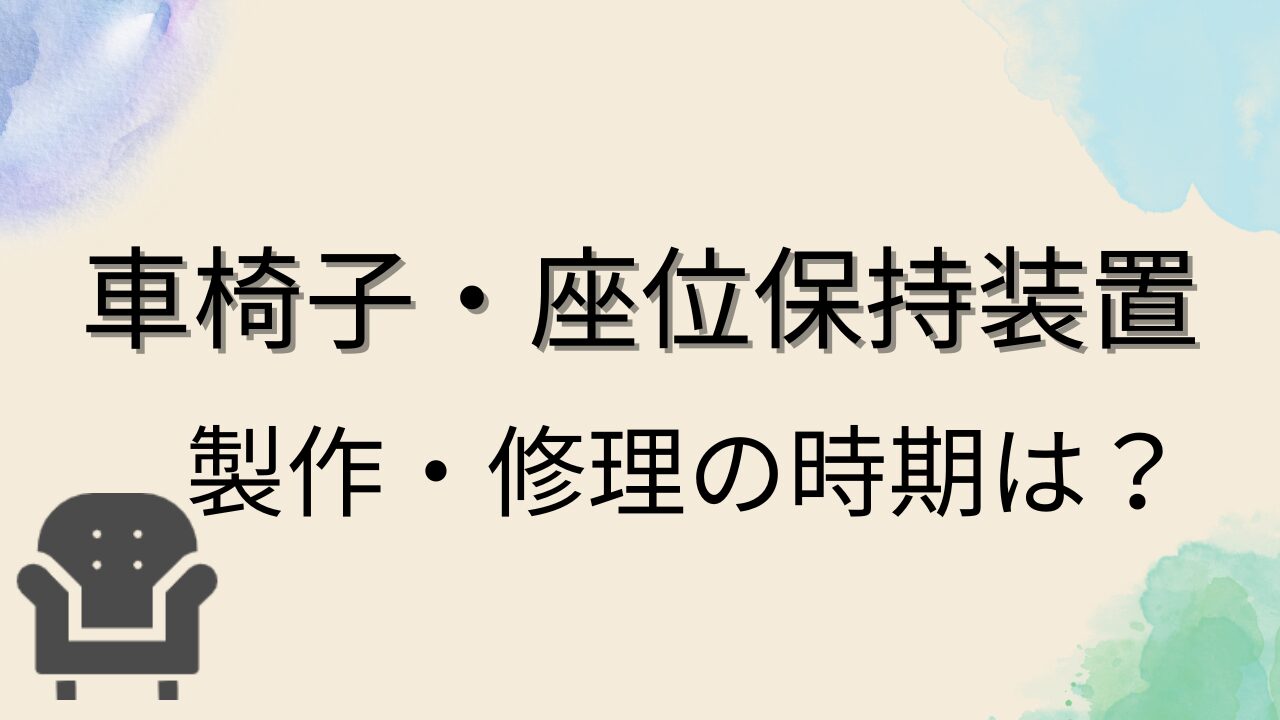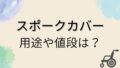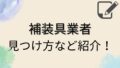・製作からどの位で作り替え出来るのかな?
・修理は制度で認められる?
補装具の会社で10年以上事務員として働いている私が、上記のようなお悩みを解決出来る記事を書きました。
車椅子や座位保持装置を何年も使っているが、全体的に古くなってきたのでそろそろ作り替えたい……。
とお悩みの方は多いかと思います。
製作や修理で利用する補装具費支給制度ですが、実は作り変えなどの時期が決まっているんです。
詳しく解説しているので最後までご覧下さいね。
車椅子の作り変えは何年ごと?

車椅子は何年ごとに作り変えが出来るのか、まずは解説します。
車椅子の作り替えは6年ごと
車椅子を新規で作ると、次に新しく作れるのは6年後になります。
これは厚生労働省が制定している補装具費支給制度で定められているんです。
ちなみに、車椅子を作り替えたい際の、メーカーやフレーム選びには下記の記事を参考にしてみて下さいね。
車椅子を2台作る事は出来ない
『2台作っておけば、片方が壊れた時に困らないじゃない?』
と思う方もいるかもしれませんが、2台を同時に作ることは出来ません。
これも制度で決められているんです。
例外として学校や施設に通っている方の場合、1台ずつ作ることも出来ます。
ただ市町村によって判断基準が変わってくるので、確実にとは言えないんですが……。
座位保持装置の替え保持装置の変えは何年ごと?

座位保持装置は何年ごとに作り変えが出来るのか、見て行きましょう。
座位保持装置の作り替えは3年ごと
座位保持装置は3年ごとに作り変えが出来ます。
車椅子は6年なのに対しなぜ3年なのかというと、クッションなどがへたりやすいから。
クッションがダメになると姿勢に影響が出て、呼吸困難や病気の進行などを早めてしまう可能性があります。
なのでクッションなどは3年ごとに変えることが出来ます。
座位保持装置は2個同時に製作は可能?
座位保持装置は全く同じ物を、同時に2個製作する事は出来ません。
そもそも座位保持装置とは何?
座位保持装置について解説しておくと、姿勢を保持する為の補装具といった感じです。
座位保持装置付き車椅子を車椅子をオーダーメイドで作る場合、クッション部分はその人の身体に合うように寸法を取ったり型を取ったりします。
車椅子以外だと、家で過ごす時に座る椅子などがあります。
車椅子や座位保持装置の修理は制度で認められる?

ここまで作り替えについて見てきましたが、修理については決まりがあるの?
という疑問にお答えして行きます。
修理も補装具費支給制度で認められる
車椅子や座位保持装置の修理も、補装具費支給制度を使用することが出来ます。
修理の時期に決まりはある?
基本的には、修理のタイミングについては定めがないです。
タイヤがパンクしたりフレームが折れたりなど……。
補装具の不具合は日常生活に大きな影響を与えてしまうので、修理が必要になったタイミングで制度を利用することが出来ます。
補装具の作り変えや修理に関するよくある質問
事務員として10年以上働いていて、補装具の作り替えや修理に関してよくある質問をまとめてみました。
製作や修理をしたいが市町村に申請するのが面倒な時はどうすればいい?
補装具の製作や修理にかかる費用を市町村が負担してくれる補装具費支給制度ですが、デメリットもあります。
それは、申請から支給決定が下りるまで1~2週間かかること。
補装具業者は支給決定が下りてからでないと作業を開始出来ないので、1~2週間は不具合を抱えたまま生活しなければいけないんですよね。
すぐ修理したい! とお客様に言われた時に私が案内しているのが、自費での製作や修理。
お金はかかりますがすぐに作業に取り掛かることが出来るので、1つの手段として覚えておいて損はないと思います。
年数が経ってるが修理と新規製作のどちらがいい?
車椅子の場合を例にお話ししますね。
製作から6年以上経過している場合は、基本的には新規製作の方がいいです。
というのも、車椅子全体にガタが来ているだろうし、身体の変化などもあるので合わなくなっている可能性があるから。
もうすぐで6年といった時期の場合は、少し先を見据えた方がいいかと思います。
例えば、病気の進行具合や手術などを控えているのかなど。
遠くない未来に体に大きな変化が起こりそうな場合は、製作ではなく修理で対応してみるのもいいかと思います。
まとめ
車椅子と座位保持装置の、作り替えと修理のタイミングについて解説しました。
時期を把握しておくと『あ、そろそろ新しく作れるな』と分かるので、常に体に合った補装具を使うことが出来ます。
頭に入れておくと役立ちますよ。